事実
宮代へ2
2012/06/24
姫宮神社
姫宮神社は旧百間領の総鎮守で、祭神は多紀理毘売命・多岐津比売命・市杵島比売命の3柱を祀る。社伝では、桓武天皇の孫の宮目姫が当地に立ち寄った際、紅葉の美しさに見とれ、突然の病で亡くなったことを、後に慈覚大師円仁がこの話を聞き、姫の霊を祀ったのが始まりであるともいう。また、一説には、延長5年(927年)成立の『延喜式』に記載される「武蔵国埼玉郡宮目神社」は当社のことであるという。
当社の本殿は、基壇の銘によると「正徳5年(1715年)4月吉日」とあり、その頃建立されたと推定され、建築様式からも証明されている。一方、拝殿は、海老虹家梁に文久3年(1863年)の銘が記されている。拝殿内には絵馬が多数掲げられており、一部は町の指定文化財に指定されている。
また、かつて所蔵していた応永20年(1414年)銘の鰐口は、現在、町の指定文化財として当社の別当寺であった前原の宝生院が所蔵する。本殿の東側に八幡社が祀られている。元は別の神社であったが、明治35年(1902年)当社に編入された。なお、八幡社は周囲より2メートル程小高くなっており、かつて埴輪片が出土したことから古墳であると推定される。





西光院
西光院は、真言宗智山派の寺で、かつては京都醍醐三宝院の直末であった。百間山光福寺と号し、奈良時代の僧行基の草創であると伝えられている。当時の阿弥陀如来像及び、観音像、勢至菩薩像の両脇侍からなる三尊像は、平安時代末の安元2年(1176年)に作られた。これれらの仏像は国の重要文化財に指定され、現在東京上野の国立博物館に寄託・展示されている。
中世には、岩槻城主太田氏の祈願所とされ、江戸時代の初期、徳川家康は寺を中興2世の日誉上人に深く帰依し、寺領50石と栗田焼きの葵紋入の茶碗を寄せた。この茶碗は、寺宝として現存している。
一方、当寺は御影供寺としても知られている。御影供というのは弘法大師空海を供養する法要のことで、入定された旧暦3月21日にちなみ、当寺では毎年4月21日に行なっている。また、新嫁は、初めてむかえるこの日に(4月21日)花嫁姿で参詣したことでも広く知られている。


五社神社
五社神社は、以前、五社権現社もしくは五社宮とも言われ、熊野三社(熊野坐神社、熊野速玉神社、熊野那智神社)、白山、山王の五社)を等間隔に祀ったことからその名が起こったと言われている。祭神は、天之忍穂耳命他7柱である。
創建年代については、別当である西光院が火災にあったため明らかでないが、現在の本殿は、桃山時代の文禄、慶長(1592~1614年)の建築と推定されている。本殿は五間社流造りで、正面に向拝をつけ、蟇股に牡丹、竜、鳳凰、猿、虎などの彫刻が施されている。大正年間にカヤ葺きからトタン葺きに替えられ、昭和49年の解体修理のとき銅板葺きにされた。また、それぞれの社には、元禄14年(1701年)5月吉日の年号がある銅製の御神鏡がある。江戸の鏡師二橋伊豆守藤原吉重の作である。
拝殿前には文政3年(1820年)に建立された当地の俳人中野南枝の句碑があり、拝殿内の正面にも同時期の俳句絵馬が奉納されている。なお、本殿は昭和37年3月県指定の文化財になっている。



その他

なぜか猿田彦命の碑が道端にありました。こういうのは北海道にはなかったので、不思議です。

不思議なオブジェが草原に転がっていました。

元墓地なのか、それとも見捨てられた墓碑なのでしょうか。





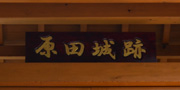





コメント