事実
京都へ2
2012/08/19
京都を歩いているとすぐに歴史とぶつかります。そんな足跡です。
大聖寺庭園
門跡尼寺である大聖寺の庭園は、当寺所蔵の日記によれば、1697年(元禄10年)明正天皇の河原の御殿から材料を移して作庭されたものである。その後、いくらかの改修があったとみられるが、東西方向に長くのびた枯流れを中心に展開される庭景は、御所ふうの優美さを感じさせる。江戸時代中期の記録が残る、優れた意匠の庭園として貴重なものであり、昭和60年6月1日、京都市指定名勝とされた。



京の町

光照院門跡
1365年(延文元年)後伏見天皇の皇女進子内親王が室町1条北に天台・禅・律・浄土4宗兼学の道場として、創建。応仁の乱の後、現在地に移転した。
この地にもと持明院殿の持仏堂安楽光院がたっていたため、一時は安楽光院とも称した。開山以来、代々の皇女が法系を継ぎ、1789年(寛政元年)に光格天皇が常磐御所の称号を与えた。その名にふさわしく、代々の宮お手植えの五葉の松が、書院の庭に繫りあっているのも類をみない美しさである。

妙覚寺大門
妙覚寺は北竜華具足山と号し、京都日蓮宗各刹三具足山及び京都十六本山の一つである。南北朝時代の1378年、竜華院日実上人により、信徒で豪商の小野妙覚の四条大宮の邸に創建された、その後、二条衣棚に移ったが、豊臣秀吉による大規模な都市改造の際に、この地に移建された。一時は、本能寺とともに、織田信長の上洛時の宿舎とされ、千利休による茶会も催された。
この大門は、寺伝によると、秀吉が1590年(天正18年)に建設した聚楽第の裏門を1663年(寛文3年)に移建したものといわれており、西本願寺の飛雲閣、大徳寺の方丈・唐門などとともに数少ない聚楽第の遺構である。城門特有の両潜扉を持ち、梁の上には伏兵を配置できる空間が設けられている、建築史上興味深い建物である。


千利休居士遺蹟 不審庵


京の町

首途八幡宮
宇佐神宮(大分県宇佐市にある八幡宮の総本宮)から八幡大神を勧請したのが始まりと伝えられ、誉田別尊(応神天皇)、比め大神、息長帯姫命(神功皇后)を祭神とする。もとの名を「内野八幡宮」といい、平安京の大内裏(皇居や官庁があった場所)の北東に位置したため、王城鎮護の神とされた。
かつて、この地には奥州(東北地方)で産出される金を京で商うことを生業としていた金売吉次の屋敷があったと伝えられ、源義経(牛若丸)は奥州平泉に赴く際に、吉次の助けを得て、ここで道中の安全を祈願して出発したといわれている。「首途」とは「出発」を意味し、この由緒により「首途八幡宮」と呼ばれるようになった。このことから、特に旅立ち、旅行安全の神として信仰を集めている。


武勇と仁義に誉れ高き英雄、源九郎義経(幼名牛若丸)は高倉天皇の時、1174年(承安4年)3月3日夜明け、鞍馬山から、ここ首途八幡宮に参詣し旅の安全と武勇の上達を願い、奥州の商人金売橘次に伴われ奥州平泉の藤原秀衡のもとへと首途(旅立ち)した。この地に橘次の屋敷があったと伝えられ、この由緒により元「内野八幡宮」は「首途八幡宮」と呼ばれるようになった。時に源義経16才であった。













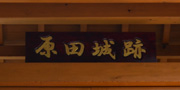


コメント